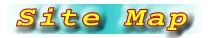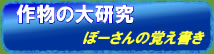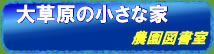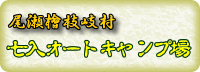作物の大研究
目 次
はじめに
家庭菜園なんてこともやったことがないので、何をどうつくればいいのかということがまったくわかりません。だからコツコツと調べることから始めなければならないのです。身近には農園主のおくちゃんがいるからいいのですが、おくちゃんの話を鵜呑みにするのもかなり危険だと思っているのです。いかにおくちゃんが野菜栽培の経験が長いといっても、所詮家庭菜園であります。やはりここはプロの百姓に聞くのがいちばんでありますが、身近にそんな人は一人もいないのであります。正しくは無農薬・無化学肥料で生計を立てているプロの農家の知り合いがいないといったほうがいいです。したがって必然的に本とWEBから情報を得ることになります。現時点(2010/1)では調べるだけで実践はしていません。おいおい実践した時の結果や経緯も含めて掲載していきたいと思っています。
また、農業なんてやることは同じだと思っていたのですが、100人の農家がいれば100のやり方があるというのも始めて知りました。今わかっているのは、農薬も化学肥料も使う在来農法というものと、無農薬で有機肥料を使う有機栽培というものがあり、それに輪をかけた無農薬でしかも肥料さえ使わない無農薬無肥料の自然栽培というものがあることを知りました。在来農法の農薬と化学肥料を使うものは最初から選択肢にはありませんでしたが、悩ましいのは後の2つです。有機肥料を使うのか使わないかの選択であります。今のところ、無農薬・無肥料の自然農法は実験を重ねることによって将来的にすべてそちらに移行していこうと思っています。ここらあたりはどうなるかわかりません。
TOPどんなことをしても無農薬・無化学肥料は鉄則です。
はじめて農作業をやって感じたことでありますが、作る側と買う側の立場が違えばこれほど見方が違ってくるのかということです。これまで滅多にスーパー等へ買い物などいく機会もありませんでしたが、昨年は農場での自炊生活を3ヶ月あまりやらざるを得なかったわけで、どうしても買い物にいかないわけにはいかなかったわけであります。そこで、一番感じたのは売られている農産物の安さであります。それは驚きに近いものでありました。
毎日まいにち野菜をつくるための農作業を繰り返しているわけでありますが、慣れないとはいえ、それなりの肉体労働であります。まだひとつもまともな野菜を作ったわけではありませんでしたから、自分がつくろうとしている農産物の値段なんて考えたこともありませんでした。むしろ、はたして、まともなものが作れるのかどうかだけが気がかりだったわけであります。
そんななかで目にした野菜の価格の安さにはには愕然とするしかありませんでした。どうしたら、これほど安い値段で提供できるのかが不思議であります。消費者の手に渡るまでは多くの流通を経ているわけで、それらの流通各社でも利益は取ってあの値段でありますから、はたして農家の手にするお金はどれほどのものだろうと人ごとながら心配になってしまうわけであります。
これまでは、売られている野菜は安ければ安いほどいいわけで、高ければ買わないだけでありましたから、立場が変わるとここまで変わってしまうわけであります。どうやってこの安さを実現しているのかといえば、普段の農家の努力以外にないと思います。頭がさがります。
これだけの安さに抑えるには大量生産するしかありません。まずは徹底的に機械化して、単一の作物を大量に生産するのです。機械化するということは、化学肥料を投入して、農薬で病虫害を防がなくてなりません。もはや農産物は工業製品と何ら変わることがないのだと思います。別にそれらの農法に文句をつけるつもりはありません。だってこれまで、それらの安価な農産物を摂取することによって生きながらえてきたのですから感謝にこそすれ、偉そうに能書きをたれるつもりはこれぽっちもないのであります。
農業で生計を立てるというのは前述した方法しかないのかも知れないとも思うのであります。このように書いていますが、それですら、普通はできません。だってそれだけの設備投資も必要だしノウハウも必要となるのです。最初から私たちはどう望もうと在来農法はできないということなのであります。
だから私たちがやろうとしている農業は最初から「儲け」という言葉からは見放されたものなのであります。ですから機械も使わないし、単一作物を大量に生産するということもできません。農薬を買う金も化学肥料を購入する費用も勿体ないということになるわけであります。私たちが身の丈にあった農業をするとなると、どうしたって家庭菜園の少し大きなものということに必然的に落ち着いてしまうけであります。
だから無農薬・無化学肥料は鉄則だというよりも必然だと言い換えたほうが正しいのかも知れません。
TOP失敗したことも成功したことも、その課程を詳細な記録を取って
このページに貼り付けるようにします。
私は農業のまったくの素人だということを随所でいっていますが、素人ですから、より多くのことを学ぼうと思い、書籍やネットそれに知人にあたって私なりに調べました。ま、そこはどこまで行っても所詮素人ですから、にわかに集めた知識なんていうものはたかが知れています。苦労して集めた知識や情報は実践の課程でもろくも失敗することもあろうかと思われます、しかし、これしかド素人には手段がないのです。
ですからこのページはこれまで集めた知識や情報・技術をとりあえず置いておく倉庫のようなものと考えてなるべく可視化をはかってこれからの農作業に役立てるのは当然であるとともに、実践の様子も事細かくデータを集めて広く公開していこうと思っています。このサイトでは最重要なページになるのではないかとも思っています。
また、学生でいえば今年(2010年)から入学したようなものであります。大学は4年間の学ぶ場であります。それに必要とあれば2年間の大学院という手もあります。ですから今後少なくても4年間まじめに勉強をしていけばかなりの、知識と技術を学べるとも思います。どんなことでも4年ぐらい懸命に頑張ればモノになるのではないかと思います。そんな気持ちでコツコツと勉強を重ねていきたいと思っています。ですから多分このサイトも最初に書いてあることが、勉学を通して少しづつ変化していくこともあり得ると思います。いや、自分の現在の認識が変化していくのは当たり前のことと考えます。4年後のサイトと今のサイトを比較してみたいもんだとも思っています。
TOP植えたい野菜リスト
一応百姓なるものを目指しております。米しか作らない、いやつくれないのは一姓ということになります。もっとも現在は何も作っていないのでそれこそ零姓ということになるでしょうけれども。だから出来うる限りにおいて、百の作物をつくるべき努力を重ねていきたいと思っているのです。以下につくりたい作物のリストを思いつくままに並べておきましたが、100の作物の名前すら思いつかないのが本当のところであります。先行きどうなるのかまったくもって不安であります。
さて植える作物は何にするかということになりますが、ここは自分でも料理できるカレーライスの材料は絶対に植えなくてはなるまいと強く思うのであります。そこでカレーの基本材料を並べてみますと、じゃがいも・人参・たまねぎとなるわけであります。もちろんその他の野菜をいれても構わないのですが、この3つはカレーには欠かせないものだと思うわけであります。考えてみるとこの3つの作物は保存も利きますから、カレー以外でもかなり役にたつもので、なんだか野菜の王様的な位置づけてはないかと考えるのでありました。
- 大豆
- にんにく
- トウモロコシ
- 鶏の飼育
- じゃがいも
- 人参
- たまねぎ
- キュウリ
- なす
- ピーマン
- いちご
- スイカ
- 生姜
- シソ
- 里芋
- ネギ
- オクラ
- トマト
- ミニトマト
- 大根
- ゴボウ
- 青梗菜
- 小松菜
大豆
大豆についてはかなり前から注目をしていました。無料栽培をやるにしても有機栽培をやるにしても緑肥と考え方は重要だと思ったのです。特に無肥料でやろうとした場合は大豆の栽培は大豆を収穫するということよりも緑肥を施すということを考えますと最重要作物ということになります。
醤油・味噌・納豆・豆腐といつも私が何も気にしないで食べているものでありますが、大豆で作られた食品がかなりの部分を占領していることに気づかされます。もしかしたら大豆がなければ私の食生活は成り立たないのかもしれません。「大豆は畑の肉」と呼ばれるほど栄養価の高いものだそうです。その大豆の95%以上は輸入によるそうなのであります。たぶん大豆は日本で栽培してもお金にならないからこうなっているのだろうと思います。あえて来年は作物を植えていない空き地の部分には植えられる限りに大豆を植えてみようと思っています。日本ではほとんど大豆を作っていないわけですから、採算ということを考えるとまったく合わないということなのでしょうけれども、採算に合う合わないなんてものは最初から無視してのことになります。
最初に大豆に着目したのは、奇跡のリンゴ―「絶対不可能」を覆した農家・木村秋則の記録のなかに無農薬・無肥料での栽培のなかにでてきたからであります。また、自然栽培ひとすじに
のなかにも詳しく述べられていました。豆科の作物は根粒菌というもので、空気中の窒素を土の中にため込むことをするらしいのであります。豆といっても様々なものがあるらしいのですが、なかでも大豆の効果が一番らしいというのを目にしたことにあります。それなら使わない手はないということで、農園では大豆を土壌改良のための緑肥としても使用することにしたのであります。だからお金になるならないはあまり問題にならないし、肥料として効果を一番重要視しているのであります。とはいってもやはりせっかく植えるのですから、収穫物としての大豆をこの手に取ってみたいというのはごく自然な感情かと思います。
しかし、いつものことでもありますが、この時点では大豆の種類とか栽培の仕方とか植える時期とかがまったくわかっていないのであります。だいたいにして、枝豆が大豆だったなんてことも知らなかったわけであります。このサイトにその研究を掲載しながら勉強していくことにします。
直まきか定植か
最初ものすごく簡単に簡単に考えており、畑全体をトラクターで簡単に耕し、そこに豆を時下まきにすればいいではないかと考えた。これは基本的に豆ごときにあまり肉体労働をするのが嫌だという思いと、ものごとを知らない浅はかな考えからきていた。しかし、いろいろと調べていくとそれほど単純なことではなく、これこそ失敗につながる考え方なのだという結論に達した。
たんに直まきをするというのは、上野公園にて鳩に大量のエサをばらまくことに等しいことを後にしることになったのです。農園の周辺に鳩が見あたらなかったら、直まきという方法もあるのですが、残念ながら農園の周辺には数十羽という山鳩が生息しているのを見たのであります。
大豆の栽培において、最大の難関は蒔いた種をある程度成長するまでにいかに鳩から守るかにつきるということであります。
植える時期
参考文献・参考サイト
みんなの農業広場(麦・大豆編) TOPにんにく
にんにくは昨年10月の終わり頃に植え付けました。にんにくは農園主のおくちゃんが3年にわたって栽培していたものを種としてわけてもらい使用しました。順調にいけば7月ごろには収穫できるはずであります。どのぐらい取れるかはまだわかりませんが、結構楽しみであります。
にんにくを植え付けるのには苦労しました。なにが一番大変だったかといいますと、使わなくなった田んぼを畑に転換する作業であります。
TOPトウモロコシ
トウモロコシを植える理由は最終的に鶏を飼って、たまごと鶏肉を手に入れたいと考えているのです。もちろんトウモロコシだけを食べるという食べるという目的もありますし、出荷もして幾ばくかの現金も手に入れたいとも思ってはいますけど。
鳥を飼うのに、エサを別途購入するというのでは飼わないほうがいいとも思うのであります。鶏は雑食性ですから余った野菜などをやって育てたいと思っているのです。
TOP鶏を飼おう
鶏を飼おうと思ったのは「脱サラ百姓背水の陣大豆づくり奮闘記」を読んだのがきっかけでありました。そういえば幼かった頃にはどの家にも鶏が普通に飼われており、字のごとく普通に庭に放し飼いにされていたことを思い出したのです。エサと水やりと採卵は幼かった私たち兄弟の役目でありました。もうほとんどのことを忘れてしまっていますが、鶏を飼うのに何ら難しいことは無かったような気がします。そこでいくら農業の素人であっても鶏ぐらいは飼えるだろうという発想であります。
鶏を飼う動機のもうひとつは、まったくの素人百姓で、無農薬での栽培を目指しているので、最初から見場のいい野菜をつくるのは困難だと考えたのであります。見場の良い野菜は当然自家消費して残ったら売りに出して処分しますが、売れそうにないものは捨てるしかないけど、それではいかにも勿体ないので鶏に与えたらどうだろうかと考えたのです。そうすれば一切の無駄も生じないわけであります。それに土壌改良のために豆を植えることにしています。それにトウモロコシとくれば配合飼料なるものを購入しなくても、無農薬の飼料を与えて、広い鶏舎で平飼いしてノビノビと育てれればおいしい卵を毎日のように食べることもできるし、案外高い値段で引き取ってくれるのではないかと思っているのであります。
それに今のところは、主力となるのは有機栽培でありますが、苦労して鶏糞を貰いに遠くまでいく必要がなくなるわけでもあります。これこそ理想的な循環農業ということではないでしょうか。こう考えてみる本当に良いことづくめのように思われてなりません。実際に飼ってみれば思わぬ問題もでてくるのでしょうが
一昨日山形に住む妹から電話があった。「雪は降っているか?」開口一番に飛び出した私の言葉だ。「今は降ってないけど、とにかく寒い、道路もきんきんに凍っている・・・・」そうかそうか、寒いか、寒いだろうな。雪の量も結構多いそうだ。そうかそうか雪の量も多いのか。寒い日がつづきます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。 ネットで比内地鶏のことを調べていたら以下の書き込みを発見した。 >「東京のデパートでは百グラム六百五十円、ー羽八千円で売っている。世界一高く、日本一うまいのが比内地鶏。名古屋コーチン、薩摩地鶏と比べても味は絶対に上だ」と大沢清治町長は力説する。 それでさっそくおくちゃんにメールをした。以前から鶏は飼うべしと思っていたのであります。 私:「おいおい、これはやっぱり鶏の飼育はするべきでしょう。こんなに高いものだとは知らなかった。でも気になったのはF1だということです。F1ってことは自分のところで卵から孵すということができないってことですかね。毎年ヒナを業者から購入しなければいけないってことでしょうか。それは嫌ですね。」 おくちゃん:「・・・・・・。比内鶏は自家で孵化し育成することは原則できません。雛の入手は2箇所あり比内鳥の原種と掛け合わせてF1を生産したものを購入している。原種は天然記念物で販売はできません。餌も決まっていて儲かりません。手間代です。販売するなら仕入れた方が手っ取り早い・・・・。」 という返信が返ってきました。農業には聞き慣れない言葉が多い。まずは言葉に慣れることから始めなければならない。ここで疑問に思うのはF1という言葉です。そこでさっそくググってみることにした。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1110478471F1は一代雑種のことです。 FはFilialの略です。 Filialは単語としては「子の」とか「子としての」を意味しますが (単語の意味は英和辞典調べたまんまですが・・・)、 このように遺伝的分野での用語として用いられる場合は「交雑(交配)されて誕生した子(子孫)」を意味します。 F1であれば交雑された一代目ということになります。 交配させて生まれた子の特性が「子の子(孫)」にうまく継承されないが、 遺伝学的に安定した品種の両親が揃っていれば 安定して同じ特性の子が生み出せる場合に用いられるようです。 (品種Aと品種Bを掛け合わせると常にCの特性を持った子が生まれるが、 Cから生まれた子供はCの特性をうまく継承しない場合) 有名な例では、比内鶏とロードアイランドレッドを交配させた「比内地鶏」もF1です。 これは交配させることでしか生み出せないためです。 そのため「比内地鶏」を生み出すためには 純血種の「比内鶏」と「ロードアイランドレッド」がいなければなりません。 「比内鶏」の場合は天然記念物のため食べるわけにいかないのと、 「比内鶏」は肉質は良いものの繁殖力が弱く体も小さいため食用には向いていなくて、 繁殖力が強くて体の大きい「ロードアイランドレッド」と交配させて 体が大きく肉質も良いものを生み出し、食用とするためこのような方法が用いられています。私としては、卵から鶏を孵して鶏の雛を購入することなく、無農薬で育てたとうもろこしや豆を飼料として与えるということを妄想していたわけですので、比内鶏は却下となるわけであります。しかし、これにともなって他の鶏の品種を見当しなければならなくなったわけであります。 はやい話が夜店で買ったひよこを育ててもいいのですが。たまごを生めばなんでもいいけどね。 そうか、ここに出てくるロードアイランドレッドでいいじゃないか。そうだそれでいいよ。ってそんなもんどこで売ってるんだろうか。まさかペットショップにいけなんてのはないよね。またあらたな問題がでてきてしまったな。 TOP
参考文献・参考サイト
農家が教える混植・混作・輪作の知恵―病害虫が減り、土がよくなる

一昨日半月ほど待たされた待望の農家が教える混植・混作・輪作の知恵―病害虫が減り、土がよくなるが届いた。さっそく中味をつらつら斜め読みをする。これは期待した以上のことが書かれているのではないかと直感する。副題には「病害虫が減り、土がよくなる」とあるではないか。農園では決して農薬および化学肥料は使わないと高らかに宣言してしまっている。別に高らかに宣言しなくても、まったく農薬および化学肥料は使う気はないのだからいいのだけども。もし農薬を使い化学肥料を使った野菜を栽培するのなら、別に俺たちが作らなくても、スーパーにいけばかなり安くしかも見場のいい野菜が豊富に並んでいるのだから結構なことではないかと思うのだけれども、どう思いますか。
でも本音をいうとね、農薬を使わないで病害虫に冒されない健康な野菜が作れるのかまったく自信がない。そこでいろいろなことを研究しはじめたわけであります。緑肥を使うってのもわかったし、いろんな野菜を混ぜて植えるのが効果的であるというのも最近知ったわけであります。これからますます研究を深めて春からの実践に備えたいとおもいます。
しかし、農業で使う言葉も半分以上はわかりませんね。まずは言葉を理解することから始めなければいけないかも知れません。それに、害虫の名前も姿すら知らないしね、病気の名前も、その病気にかかるとどうなるのかもさっぱりわかりません。思っている以上に無農薬での栽培はなかなか手強いのかも知れないですね。
この本のなかに「コンパニオンプランツ」なんて言葉が出てくるけど、最初なんのことかさっぱりわからなかったけれども、「共栄作物」というらしいのであります。フムフム・・・・・・。さらっと斜め読みした限りでは、あんまりにも簡単に片付け過ぎかもしれませんが、理想的な農法は家庭菜園なんですね。せまい圃場に所狭しとなんでもかんでも植えてあるのが理想みたいですよ。
しかし、家庭菜園は趣味でやっているから、できるけどもそれを儲けのペースに乗っけようとしても、あまりに手間ひまがかかりすぎるので無理ということになります。
スーパーであれだけ安い野菜が売られている陰には、もちろん農家の方のたゆまぬ努力もありますが、大量生産という現代農業の技術があるわけであります。広大な農地に、単一の作物を植える。それはすべて大型の特化された機械を使用する。当然そこには大量の農薬と化学肥料をこれでもかと投入せざるを得ないわけであります。
別にこれらの農法を否定しているわけではありません。これまで散々それらの安価な野菜にお世話になってこれまで生きてきたのですから感謝こそすれ、文句をいう筋合いなどというものは少しもありません。
安全安心な食物を口にしたかったら、自分で栽培することだとおもいますね。それにつきると思っているのですが、いかがでしょうか。
目次
- カラー口絵
- 伊勢村文英さんの混植畑
- 混植、混作で作物が育つ
- 家庭菜園の混作
- 雑食緑肥で土作り
- 焼畑の輪作と文化
- はじめに
- Part1 混種、混作、間作で作物をつくりやすく
- 【図解】混植・混作
(病気や虫が減る組み合わせ/バンカープランツ) - 【図解】知って得するコンパニオンプランツ大集合!
(まずはおなじみネギ・ニラ混植/相性のいい作物) - 【図解】香り混植 虫が好きなニオイ、嫌いなニオイ
害虫は作物のニオイで寄ってくる/害虫を減らす「香り混植」いろいろ/虫の成長を阻むニオイ/促すニオイ - 間作、混作で土が流れない
- カマキリがいる畑は害虫が少ない
- コンパニオンプランツ(共栄共作)の知恵
- 混播、混植で無農薬
- 混播、混植、米ぬか活用で健康野菜
- 天敵が増える畑のデザイン
- 作物の相性をいかして混作・輪作
- ハーブでねぎのスリップス・ヨウトウムシを防ぐ
- トマトのオンシツコナジラミにバジル
- ハーブの害虫忌避作用と生育促進作用
- わしはコンパニオンプランツにほれこんどる
- すいか・メロン産地で広がるねぎ混種
- にんにくを一緒に植えたら、いちごのアブラムシが消えた
- ナギナタガヤ
もう病みつき!りんご、ナス、ブロッコリーの畑にも播いてみた - マルチムギ
麦を自然倒伏させてマルチに利用 - 間作業体系
うり類、トマト、とうもろこし、さつまいも、落花生・・・ - 他感物質とその農業利用
- アレロパシー物質と植物の検査
- 【図解】混植・混作
- Part2 輪作、緑肥が栽培の基本
- 落花生輪作・混作できゅうりのセンチュウ退治
- だんだん土がよくなる輪作体系
- イネ科作物の輪作で土づくり
- 水田輪作で野菜も稲も無農薬
- センチュウ害を減らす輪作組合せ
- 極上漬け物は畑の土にあった自家種と緑肥から生まれる
- えん麦、ソルゴー、レタス、小麦、とうもろこし輪作で病害虫予防
- 焼畑復活!
- 日本列島の焼畑
- 粟--大豆の連作
- Part3 輪作の原理
- 中国古代の作付体系の特色
- 奈良盆地の田畑林換栽培
- ヨーロッパの輪作体系の変遷
- 共生微生物から見た輪作体系
- 麦・ソラマメ・緑肥で窒素の流失を防ぐ
- 夏作物と冬作物の養分吸収戦略
- 土と作物間で起こるさまざまな養分吸収システム
フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略 (単行本)
出版された時から気にはなっていたのだけれども、数日前にとうとうクリックしてしまった。 まだ半分程度しか読んでないが、内容は実に面白い。面白いって書くだけではまったく書評にはなってないけど。そのうちにじっくりと読み込んだら書くかもね。 因みに作者のクリス・アンダーソンは「ロングテール」理論を提唱しました。ながらくネットに携わってきた私にとってどれも納得のいく内容でありました。 世の中はこれまで考えられなかったようなスピードで考えられなかったような社会に向かって進んでいるのに違いないと思います。 それはわかっている、わかりすぎるぐらいに理解している。でもあえて百姓をするのだ。- 第 1章 フリーの誕生
- 第 2章 「フリー」入門
- --非常に誤解されている言葉の早わかり講座
- 第 3章 フリーの歴史<
- --ゼロ、ランチ、資本主義の敵
- 第 4章 フリーの心理学
- --気分はいいけど、よすぎないか?
- 第 5章 安すぎて気にならない
- --ウェブの教訓=毎年価格が半分になるものは、かならず無料になる
- 第 6章 「情報はフリーになりたがる」
- --デジタル時代を定義づけた言葉の歴史
- 第 7章 フリーと競争する
- --その方法を学ぶのにマイクロソフトは数十年かかったのに、ヤフーは数ヶ月ですんだ
- 第 8章 非収益化
- --グーグルと21世紀型経済モデルの誕生
- 第 9章 新しいメディアのビジネスモデル
- --無料メディア自体は新しくない。そのモデルがオンライン上のあらゆるものへと拡大していることが新しいのだ
- 第10章 無料経済はどのくらいの規模なのか?
- --小さなものではない
- 第11章 ゼロの経済学
- --一世紀前に一蹴された理論がデジタル経済の法則になったわけ
- 第12章 非貨幣経済
- --金融が支配しない場所では、何が支配するのか
- 第13章 (ときには)ムダもいい
- --潤沢さの持つ可能性をとことんまで追求するためには、コントロールしないことだ
- 第14章 フリー・ワールド
- --中国とブラジルは、フリーの最先端を進んでいる。そこから何が学べるだろうか?
- 第15章 潤沢さを想像する
- --SFや宗教から、(ポスト希少)社会を考える
- 第16章 「お金を払わなければ価値のあるものは手に入らない」
- --その他、フリーに対する疑念あれこれ
脱サラ百姓背水の陣 大豆づくり奮闘記 今関 知良
この本を読む前にはもっともっと大豆づくりは簡単なものだと思っていた。鳩が大敵だという情報もすでに仕入れていたけれども、これほどまでに甚大な被害を及ぼすものだとは考えていませんでした。何も知らずに大豆づくりに参入したら著者と同じ失敗をすることになっただろうということはわかりすぎるほどわかりました。
目次
- 第1部 ボクと大豆の1000日
- Ⅰ 右往左往の大豆一年生
- 頭のなかを大豆が回る
- 野菜、米、大豆が揃ってこそ自給なんだ
- 「このあたりじゃ難しいからやめておけ」
- 畝の幅と株のあいだ
- 権平がタネ蒔きゃハトがほじくる
- 室内実験--発根・発芽の驚異
- ネットをくぐったハト
- カメムシは無視、枝豆も諦めささやかな収穫
- Ⅱ 七難八苦の大不作
- 種苗交換会--タネは命
- 2度目の苗づくり、ハトとの知恵比べ
- 定植--至福の時間
- 終日鳥追いの姿に・・・・
- 水に翻弄される日々
- 隣の里芋にヨトウムシ
- 草に教えられた自然の摂理
- ヨトウムシが移ってきた
- 日本に不向きなはずがない
- Ⅲ 感慨無量の120キロ
- 用水の導入
- ハスモンヨトウのフェロモン
- 根っこには自家肥料工場
- わが家の枝豆はチョー旨い!
- 「早く熟して」と葉取り作業
- 虫との格闘、そして懺悔
- 野ウサギを捕まえた
- 肥料工場は土に残す
- ハウスでハトの羽根むしり
- 虫くいも健康な粒も皆同じ
- トウミでゴミ飛ばし
- たとえ儲からなくたって
- Ⅰ 右往左往の大豆一年生
- 第2部 嬉しや楽しや加工品づくり
- Ⅳ マスオさんの味噌づくり
- 心ウキウキ手前味噌つくり
- 手のひら真っ赤に麹づくり
- 耳たぶ触って煮豆づくり
- 手間ヒマかけて樽仕込み
- バカにされたって楽しいミソクリ
- 自慢の天然醸造手前味噌
- 避けられない味噌のカビ
- 赤味噌、白味噌ってなに?
- Ⅴ 手探りの醤油つくり
- 塩分50%でつくる人
- 味噌より楽チン仕込み作業
- 醤油掬いザルをもらったが
- 手強すぎるカビ
- 煮沸は大間違い、対策はいたって単純
- 現代人に向かない味
- 2度目の醤油づくり
- またもや天敵のカビが
- 丸くない大豆
- Ⅵ 手づくり納豆、手づくり豆腐の幸せ
- 手作り納豆の苦い経験
- 苦節ウン年の達成感
- 納豆と豆腐の語源
- 豆腐はTPOで変化する
- シンプルな豆腐づくり
- ウソの豆腐なんてないけれど
- Ⅶ 大豆と玄米を入れたクッキー
- まずは小麦粉の話
- 必要に迫られたクッキーづくり
- わが家だけのクッキーが完成
- げん米クケットの販売
- Ⅳ マスオさんの味噌づくり
- 第3部 みんな自分でつくろうよ
- Ⅷ 子どもたちと一緒に
- 総合学習への招き
- 畑づくりは分担制
- 子どものときから男は・・・・
- みんな揃って定植終了
- 豆腐づくりは魔法のよう
- 栄養いっぱいのクッキーづくり
- 子どもたちの感想文
- 何十年ぶりの給食
- Ⅸ 大豆は日本の健康財産
- 健康は大豆のおかげ
- 大豆は食の王様
- 玄米と比べてみたら
- 大豆畑トラスト運動
- 人間動物園
- Ⅹ わが家の大豆関連レシピ
- シロウト素材料理ですが
- 豆腐を使った料理
- 納豆を使った料理
- 大豆そのまんま料理
- 味噌と醤油が調味料の主役
- Ⅷ 子どもたちと一緒に
- おわりに
農家が教える自給農業のはじめ方―自然卵・イネ・ムギ・野菜・果樹・農産加工

農家が教える自給農業のはじめ方―自然卵・イネ・ムギ・野菜・果樹・農産加工
はじめてのことをやろうとしたら、誰だって失敗はしたくないから、最初にやることは情報を収集することだと思います。それもなるべく多くの情報を収集して、自分だけは成功したいと思うはずであります。
- 第1章 新規就農のスタートをスムーズにする自然養鶏
- 1 養鶏は低コストで日銭が入り、鶏ふんも利用できる
- (1)新規就農には平飼いでの養鶏を
- (2)最小50羽で日銭と肥料がまかなえる
- 2 自然卵養鶏とは
- 3 自然卵養鶏10の条件--飼育形態と経営姿勢
- 4 自然養鶏の実際
- (1)鶏舎を建てる
- (2)ヒナを育てる(育すう)
- (3)エサの自家配合
- (4)ヒナから成鶏へ---育すう箱から鶏舎への解放
- (5)産鶏卵を養う
- (6)ニワトリの病気を見分ける
- (7)ニワトリにつく害虫とその対策
- (8)ニワトリへの獣害とその対策
- (9)駄鶏を淘汰する---動物質タンパク質食料の自給
- (10)更新する---若鶏にバトンタッチ---
- 5 寒冷地や酷暑地での飼育の注意点
- (1)
- (2)
- 6 鶏卵販売について
- (1)
- (2)
- 1 養鶏は低コストで日銭が入り、鶏ふんも利用できる
- 第2章 荒地の復元と鶏ふんなどの有機質自給肥料の利用
- 荒地の復元はゆっくり、小力的に
- 自給自足農業における農具
- 有機自給肥料の利用
- 第3章 イネ(陸稲)とムギ、野菜の自給栽培
- イネ(陸稲)とムギの輪作---主食の自給栽培
- 野菜自給栽培の基本
- 自給野菜のつくり方
- 第4章 果樹や山菜、薬草の採取と利用---手のかからない自給食物
- 手抜き放任栽培果樹の利用
- 野山の恵み---山菜、薬草の採取と利用・薬用
- 第5章 自給に活かす中島流農産加工
- 柿酢のつくり方と利用
- ラッキョウの焼酎漬け
- ウメ干し
- たくあん、カブ漬け
- 中島流副食料理法---単品・シンプル調理
- 第6章 提言---これから農業を始める方へ
- 市場原理にまどわされるな
- 一人5アールで実現する農ある暮らし